ソニー再生 変革を成し遂げた「異端のリーダーシップ」 単行本(ソフトカバー) – 2021/7/13
元ソニーCEOの平井一夫氏。
彼は、必ずしも好調でなかったソニーを立て直した功労者です。中興の祖、ターンアラウンドマネージャーとも言えるかも。
以前この記事でもちらっと書きましたが、平井氏が自身の6年間をまとめた書籍「ソニー再生」を読了したので、レビューとしてここに記載しておきます。
書籍概要

時は2012年。ソニーは絶不調の時代でした。
かつての稼ぎ頭であったプレイステーションは3が大コケ、テレビ事業も8年連続の赤字。グループ全体の連結決算も過去最大の4550億円赤字という体たらく。
2014年には品川にあった本社ビルを住友不動産へ売却。改革に聖域がないことを内外にアピールするのに抜群の材料であった。
ビジネス本にありがちな難しい言いまわしなどがなく、書籍として非常に読みやすいのも
苦しい時は原点に立ち返る

ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)の社長に就任した平井さんは、まずPS3事業の再生に着手することになりました。
平井さんは前任だったSCEA(ソニー・コンピュータエンタテインメント・アメリカ)の再生時と同じく、まずは原点に立ち返ることから始めます。
・今、PS3には何が求められているのか
・SCEが目指す成功の形は何なのか
・それを達成するため、どんな問題があり、どう対処すべきなのか・そもそも、PS3とは何なのか?SCEはどういう会社なのか?
PS3を企画した久夛良木氏は「PS3は家庭用のスーパーコンピュータ」と位置づけていました。
しかし、顧客側から見たPS3はどう見ても「コンピュータではなくゲーム」だと。一見当たり前に見えるこのギャップの認識から再定義を始めました。

コンピュータではなくゲーム機なら、49,980円では高すぎる。
49,980円コンピュータならそれなりの価格かもしれないが、ゲーム機ではまず手が出ない。ではどうするか…というところから始まったのです。
厳しい「ソニー社長」の就任
SCEを黒字化した業績を買われたのか、前任社長だったハワード・ストリンガー氏から禅定を受け、2012年にソニーグループ全体の社長に就任します。
冒頭でも書きましたが、就任時点でソニーグループ全体の連結決算は、過去最大の4550億円赤字という非常事態でした。
そこでまず着手したのは、1万人の人員削減公表。
続いて全国のソニーへ飛び回り、現地従業員の声を効きまわることでした。
どの国に行っても社員の熱量を感じる。「ソニーはこんなものじゃないはずだ」というエネルギーに、ときに圧倒されることもあった。
ただし、こうも感じた。「今のソニーは方向性を失ってしまっている」
ソニーはエレクトロニクスを軸にゲームや音楽、映画、金融と幅広いビジネスを手掛ける巨大グループとなっていたが、向いている方向はみんなバラバラに思えた(中略)
私も「ワン・ソニー」という言葉を繰り返したが、単に「ひとつになろう」と言っても何を軸に集まればいいのかが分からなくなっているのではないかと考えるようになったのだ。
160p

そこで、SCE再生時と同じく、まずは「原点に立ち返る」ことにしました。
「ソニーはどういう会社でありたいのか」
「ソニーは何のためにあるのか」
「ワン・ソニーとして何を目指すのか」
その軸はかつてソニーに存在しました。
井深大と盛田昭夫という、ソニーの創業者である両巨塔だったのです。
ソニーの前身である東京通信工業株式会社の設立趣意書には、以下の8つが記されています。
一、真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設
一、日本再建、文化向上に対する技術面、生産面よりの活発なる活動
一、戦時中、各方面に非常に進歩したる技術の国民生活内への即時応用
一、諸大学、研究所等の研究成果のうち、最も国民生活に応用価値を有する優秀なるものの迅速なる製品、商品化
一、無線通信機類の日常生活への浸透化、並びに家庭電化の促進
一、戦災通信網の復旧作業に対する積極的参加、並びに必要なる技術の提供
一、新時代にふさわしき優秀ラヂオセットの製作・普及、並びにラヂオサービスの徹底化
一、国民科学知識の実際的啓蒙活動
平井氏は、この最初の「真面目なる技術者の技能を…」の部分を何度も読み返したといいます。これこそが当時のソニーの…いや、東京通信工業の目指していた旗印であったと。
小さな工場に集まった凄腕の技術者らが、そのテクノロジーであっと言わせるような物を作り、技能を競わせる、そんな愉快な会社であろうという想いでした。
そこで平井氏は、この言葉を現代風に改めた「KANDO(感動)」と名付け、行動指針として動き始めたのです。
感動と聞くとちょっと胡散臭くなりますが、要は「すごい!と思わせること」を指します。
かつてのソニーには「すごい!」が溢れていた。
それは小型のテレビであったり、ウォークマンであったり、プレイステーションであったり…。
他の会社がやらない(やれない)ようなことを技術の力で体現して、顧客に「すごい!」「感動」を提供し続けてきたのがソニーであったと。
書籍の中で、平井氏はBCLラジオという短波放送が受信できるラジオを挙げています。
プロダクトとしては、テレビ事業の改革に取り組み始めました。
8年連続の赤字を出していた「ブラビア」などのテレビ事業は何がダメなのか?
それを探っていくと、台頭していた中国・韓国などのメーカーと差別化が出来ていない事実が浮かび上がってきます。
日本の商慣行から「数を売る」ことを軸にしていた販売方法をやめ、量より質、すなわち「KANDO」を重視した販売戦略へと切り替え、2014年度に11年ぶりの黒字化を成し遂げたのでした。
・リーダーは、聞き役に徹して従業員の熱意・不満を拾い上げること
・リーダーシップを発揮して方向性を定め、責任を取ること
・リーダーは期限を定め、ブレないこと
ちなみに
平井氏は、E3で話した「リッジレーサー」がネタにされているのを知っていたそうで、こんな紹介がなされていました。
2006年にロサンゼルスで開かれたE3というゲーム見本市でPSP(プレイステーション・ポータブル)を発表する際に、リッジレーサーを実演しながらメニュー画面で流れる声をまねて「リィーッジレーサー!」と軽くシャウトしてアピールしたことから、一部のマニアの方々から「リッジ平井」というニックネームをいただいた。
70p
関連リンク
ソニー再生 変革を成し遂げた「異端のリーダーシップ」 単行本(ソフトカバー) – 2021/7/13

参考文献
「ソニー再生」


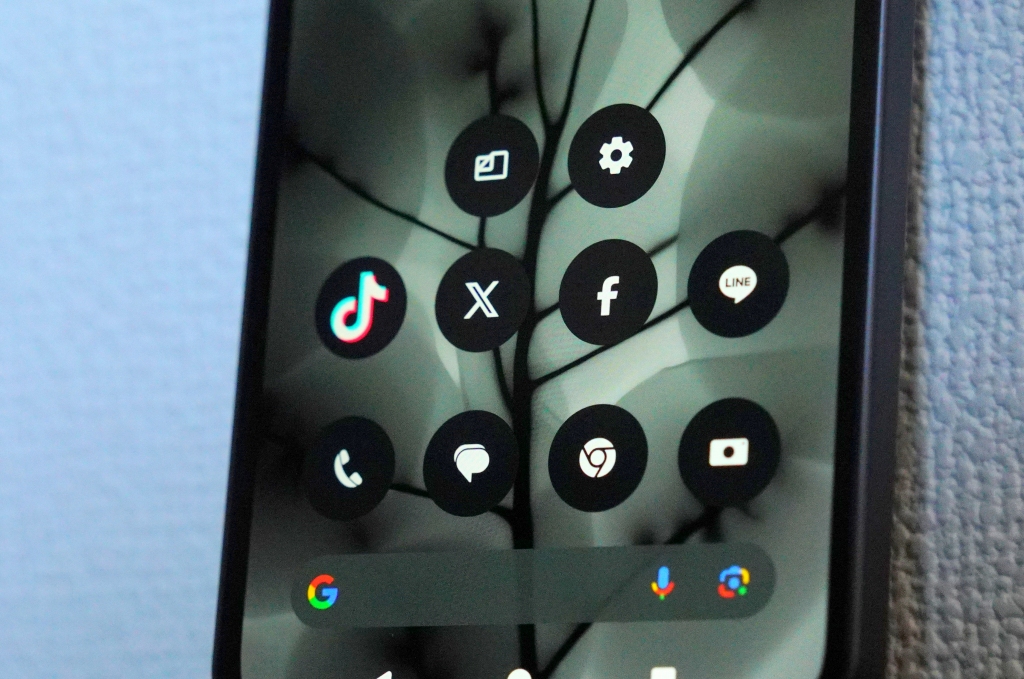




コメント