小さいお店を中心にキャッシュレスの手数料が重い…というところが増えてきました。私としては当然なことで、過度なキャッシュレス社会は必ずこうなると予感していました。
この話をすると、キャッシュレス過激派はかならずこれを持ち出します。
・釣銭を間違えるリスク
・釣銭用意の人件費
・釣銭切れリスク
・両替手数料の負担
・キャッシュレスでない事に利用控え
果たして、本当にそうでしょうか?
企業活動から見て
企業の経営からすれば、キャッシュ is キングです。
黒字でもキャッシュがなければ「黒字倒産」しますし、反対に赤字でもキャッシュがあれば倒産しません。
キャッシュレス決済の手数料は、業種にもよりますがUSENが出しているデータによると、決済額(売上高)の3%程度です。
うどん屋さんとしましょう。うどん一杯の価格は300円。飲食業の平均粗利は50%程度なので、150円です。
日本一売り上げのある丸亀製麺の場合、2023年度の売上高は1148億円です。店舗数は840店なので、以下の数字が出てきます。
①2023年度売上:1148億円
②2023年度末の店舗数:840店
③1店舗あたりの平均売上高:1.36億円
④1店舗あたりの1日平均売上高:37万2602円
ここに、先ほどの決済手数料を入れると…
1日の売上高:37万2602円
決済手数料(3%):1万1178円
両替手数料は、三井住友銀行の出しているデータだと
11~500枚:400円
501枚~1000枚:800円
1001枚以上(窓口のみ):500枚ごとに770円追加
釣銭間違えのリスク、釣銭切れリスクといったデータは流石になかったので割愛しますが、
先ほどのUSENのページでは「取扱高が大きければ安く、小さければ高くなる場合が多い」とあるので、小規模事業者ほど負担が大きくなるということになります。
これに加えて、決済事業者からの振込まれる売上の手数料も店舗負担となります。
表現規制から見て
VISA・マスターカードは近年、日本での決済に表現規制を強めています。これらは自民党の山田太郎議員、赤松議員をはじめ、元立憲民主党の栗原議員も問題視するなど、党を超えた問題意識が形成されつつあります。
全ての決済事業者に当てはまることではありませんが、キャッシュレスシェアの1-2に君臨するVISA・マスターカードへ手数料を”上納”するのは、「間接的に表現規制団体へ活動原資を渡している」と思っておいた方がいいでしょう。

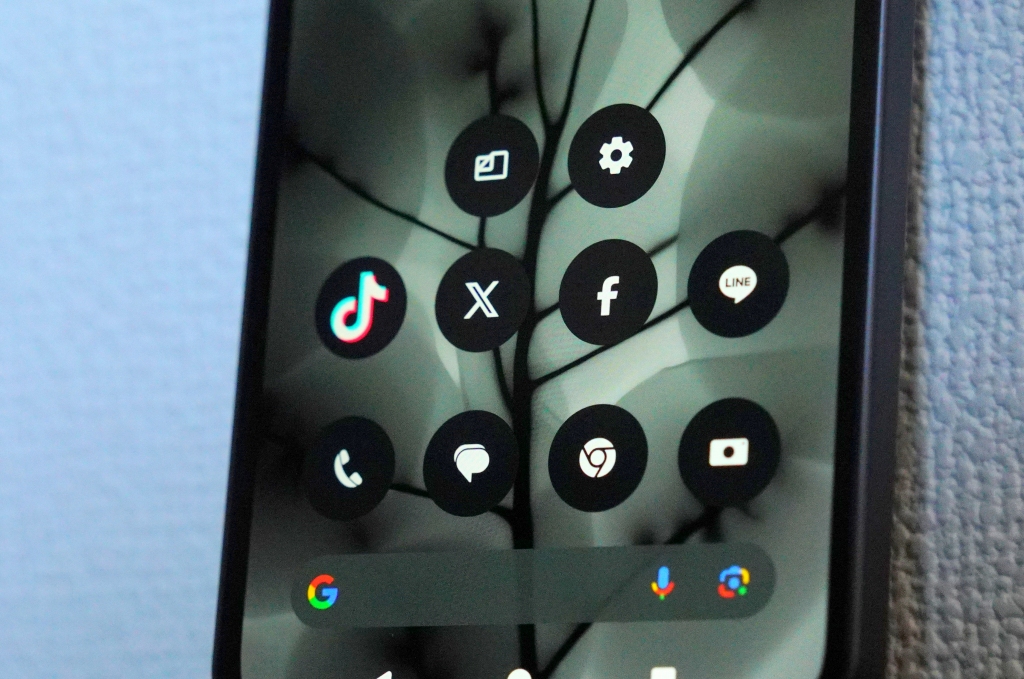




コメント