
大阪メトロになってからトイレや出口など、明らかに民営化前と比べてカッコいいプロダクトが作られるようになりました。
公営時代は必要最低限の機能を果たすものだけというか、良く言えばオーソドックス、悪く言えば退屈なものが多かったように感じます。
入札が原則→安いものに決まる
公営企業は入札が原則です。つまり安いことを競うオークションです。
同じものを作る時、安いものを採用すれば、必然的に良いものは出来ません。
随意契約という壁
随意契約とは、好きな相手と契約することを指します。普通の企業は基本的にこの随意契約という形になり、機能の良し悪しやデザイン性などは勿論、極論担当者の好き嫌いで発注することも可能です。
しかし、公営団体はこの形を採ることが出来にくいのです。
随意契約をする場合は
・金額が少額の場合
例えばトイレットペーパーなど・競争を許さない、もしくは不利になる場合
ニュートラムのシステムは住友電設しかわからないので、必然的に住友電設が担当することになります。仮に違う事業者が契約しようとした場合、システムを総入れ替えするデメリットが生じます。・緊急の場合
これは災害時や人命に係る事情がある場合。直近だと東日本大震災時はこのケースが多用されました。
少額の定義(都道府県・政令指定都市の場合)
工事や製造:250万円
財産購入:160万円
物件借り入れ:80万円
物件貸し付け:30万円
その他:100万円
また例外的ですが、国家の安全に係る重要機密事項に館しては、随意契約が認められます。自衛隊の戦車などはこれに値します。
参考文献
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%84%8F%E5%A5%91%E7%B4%84
財務省通達『契約事務の適正な執行について』(昭和53年4月1日付蔵計第875号)


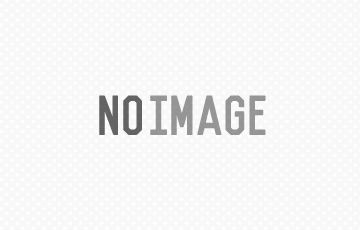

コメントを残す