大阪市には24の区があるのですが、何故か決まって北区が最初で西成区が最後に来ます。
選挙や統計などでもこの順番が割り振られており、大阪市のページでもこのような順番になっているのがわかります。
大阪市役所がある北区が一番上にあるのはわかるとして、何故西成区が最後なのでしょうか。
歴史順?
当初は大阪市が成立した4区をベースに順番に決まっていったのかなとも考えました。
大阪市が成立した最初は
・北区
・東区
・南区
・西区
の4つで、1989年に東区と南区が合併して中央区に、大淀区が北区へ吸収合併されています。
先程の一覧では北区の次点が都島区・福島区・此花区になっていますが、これらは元々北区だったエリアを含むので、北区から分区したと考えるならこの位置でも問題はありません。
此花の次が中央区、そして西区…となっていて、西区の次点が元西区であった港区・大正区なのでここまでも矛盾がありません。
・北区
都島区・福島区・此花区・中央区
(東区と南区が合併)・西区
港区・大正区
ただ、この次の天王寺区が矛盾を生みます。
天王寺区は元々西高津村・東平野町が東区、天王寺村・生野村の大阪環状線内側にあたる部分が南区となっており、1925年にそれらを編入して誕生した経緯があります。
この経緯からすると、天王寺区は中央区の次点に居ないと先の並べ方と合わなくなってしまいます…。
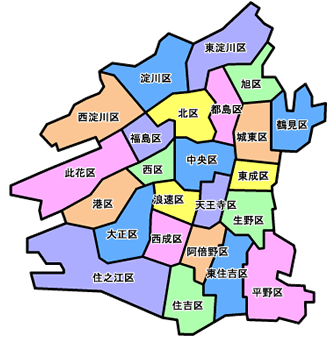
時計回りでセットしていってるのかなとも思ったのですが、これだと浪速区の次に西淀川区がこないとおかしいんですよね。
比較的新しい区である住之江区や平野区が下位にあることから、概ね誕生順となっているものと思われますが、西成区が最後である理由が全くわからないのです。
地方公共団体コード?
行政には全て地方公共団体コードと呼ばれるナンバーが割り振られているのですが、ここが由来ではないかとも思いました。
しかし国のページを見てもわかるように、一番若番が都島区で最後が中央区となっています。
北区・中央区が下にあることから、おそらくは編入合併のあった区が一番下となる法則でこうなっていると思われます。








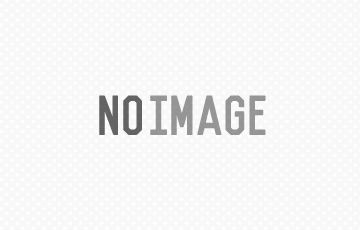

コメントを残す